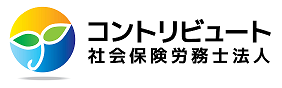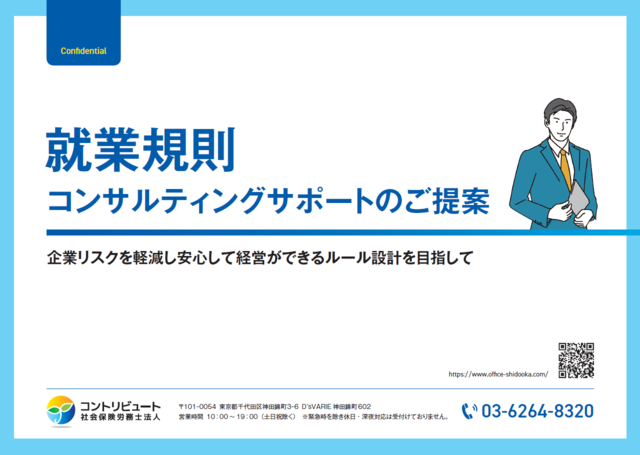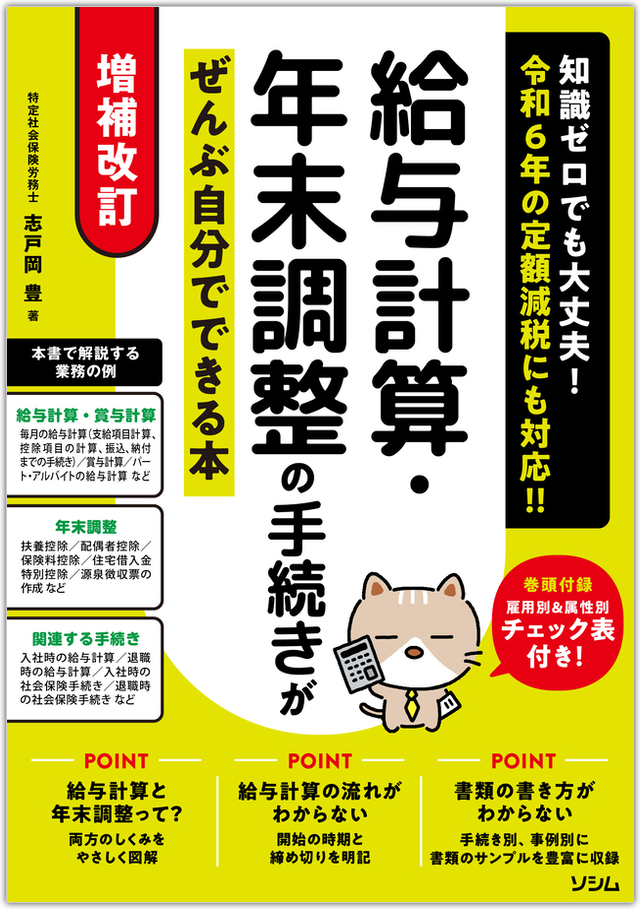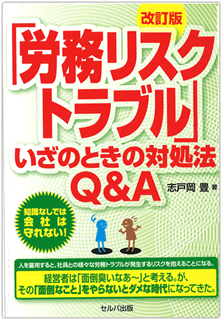就業規則の作成・変更なら東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人へお任せ下さい。
副業解禁時代の就業規則作成|副業ルールのポイントと注意点
記事更新日:2024年12月8日

- 副業は禁止した方がいいのか、認めた方がいいのか判断がつかない?
- 副業の取扱いをどうすればいいのか?
- 副業の取扱い、ルールを就業規則で規定したい。
- 社員から副業の相談があり、対応や回答に苦慮している。
副業の取扱いは時代とともに、かなり変わってきました。
以前は正社員の場合は副業の禁止は当たり前でしたが、時代は代わり、副業を認める動きも徐々にでてきています。
厚生労働省のモデル就業規則においても、副業については原則禁止から原則容認へと方向性が変わり、メディアでも取り上げられ大きな話題となりました。
このページでは、社員の副業の取扱いを就業規則で規定する際のポイントをご説明いたします。
就業規則での副業の取扱い
就業規則で副業の取扱いについて規定する会社は多いですが、実は社員の副業を全面的に禁止することはできないようになっています。
これは、社員には、会社との労働契約によって様々な縛りを受けますが、あくまでも就業時間についてのことです。
プライベートな、終業後の時間をどのように使うのかについては原則は社員の自由となります。
つまり、就業規則で副業の禁止を規程したとしても、どんな場合でもその禁止規定が全て認められるわけではなく、要件が必要になります。
副業の禁止が認められる2つのパターン
就業規則において副業禁止の定めがある場合に、その禁止規定が認められるパターンは大きく分けて次の4つになります。
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
上記のなかで①と③について、もう少し詳しく考えてみましょう。
・労務提供上の支障がある場合
労働契約の趣旨は、労働力を提供することで賃金を支払うというものです。
これは労働者側からすれば、良質な労働力を提供する義務を負っており、単純に出勤すればいいというものでもありません。
よって、副業で心身ともに疲弊した状態で出勤されても、本業の仕事に集中することはできません。
もう少し具体的にイメージしてみましょう。
私は大学時代に色々なアルバイトをやった経験がありますが、中でも体力的にきつかったのが工事現場の深夜のアルバイトです。
例えば、もっと収入を増やしたいと考えた社員の方が日中仕事をした終業後に、このような肉体的にキツイ深夜のアルバイトをして、次の日出勤したらどうでしょうか?
とてもじゃないですが、きちんと睡眠をとった社員とは労働力の「質」が変わってしまい本業に悪影響がでるはずです。
このようなパターンでは副業禁止が認められる傾向が強くなります。
・競業により自社の利益が害される場合
社員には、在職中に会社の不利益になる競業行為を行なうことを禁止するという競業避止義務というものが課せられています。
このパターンは、自社の情報漏えいの問題とミックスで問題になることも多く、会社としても一番注意しなければならないパターンです。
ライバルとなる同業他社で働くこともありますが、実はこのケースは社員が自分で事業をやって利益を得るという形の副業にも該当します。
上記の他、副業の内容が会社の信用を失墜させるような場合も禁止が認められる傾向が高いでしょう。
最も、会社の信用失墜行為については広い解釈ができますので副業が直接的にかかわるかといえば少し違ってきます。
副業禁止が書いてない場合はどうなるのか?
副業禁止の規定が就業規則に書いていない場合、または就業規則がそもそもないような場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、社員が副業をしたこと自体では懲戒処分をすることができないことになります。
ただ、副業に関係して会社の秩序を乱したといった場合や、会社の重要な情報を漏らしたという場合については、また変わってきます。
副業禁止が書いてないからといって、どんな場合においても副業が認められるわけではありません。
副業禁止規定に違反した社員は解雇できるのか?
就業規則で副業禁止を定めた場合、そのルールを守らない社員への対処をどうするかも問題です。
まず、解雇という手段をいきなり選択するかは別にして、会社が懲戒処分を社員に懲戒処分をする場合には、以下の要件を全て満たす必要があります。
1、就業規則に根拠規定があること
これは、規定を定めておけば問題ない点です。
2、懲戒事由に該当する事実があること
これは、副業禁止規定に違反したという事実があることです。疑わしいけれども証拠がない場合などは微妙なところです。
3、懲戒処分の内容の程度に相当性があること
ここが一番難しいポイントです。懲戒処分に該当する事実と、その処分の内容にバランスがとれているか、ということです。
解雇が認められるかどうかも、副業禁止規定を違反したことで会社に与えた影響の大きさが判断のポイントになります。
ここで、副業の禁止規定に違反したとして社員を解雇した事例で、解雇が認められた事例、認められなかった事例をそれぞれご紹介します。
この事例のように、副業禁止を就業規則で定めたとして、もし規定に違反した社員を解雇したとしても、その規程の有効性は個別の事案によって異なるということになります。
副業の禁止が認められた事例
建設会社の社員が、終業後に午後6時から午前0時までキャバレーで毎夜6時間の副業をしていたことが発覚し、副業禁止規定に違反したとして会社を解雇された事例です。
この事例では裁判所は、「軽労働とはいえ毎日の勤務時間が6時間に亘り、かつ深夜に及ぶものであって、単なる余暇利用のアルバイトの域を超えるものであり、副業が債務者への労働の誠実な提供に何らかの支障をきたす蓋然性が高い」として、解雇の有効性を認めています。
副業の禁止が認められなかった事例
貨物運送会社の運転手が運送先の店舗の荷物を運ぶアルバイトを年に数回したことは、「業務への具体的な支障をきたしていない」として解雇を無効とした事例があります。
パートタイマーなど正社員以外の場合はどうなるか?
副業禁止が認められるパターンの1つが「心身の疲労により本業に悪影響を与える副業の場合」であることは先に説明した通りです。
この悪影響を与える程度は当然、正社員とパートタイマーでは変わってきます。
例えば、週に3日(月曜、火曜、水曜)勤務するパートタイマーの方が、他の木曜と金曜に会社とは全く別業種の仕事を副業でしていた場合には、普通に考えて本業に悪影響がでるとは思えません。
こうなると、正社員に比べ、アルバイトやパートタイマーといった非正規社員の場合には、競業避止や守秘義務が守られている限り、副業は原則容認されるという考えになるでしょう。
厚生労働省の副業・兼業ガイドラインは押さえておく
社内で副業のルールを検討するとき、また、実際に社内で副業をする人が発生したときに押さえておきたい資料としては、厚生労働省の副業・兼業ガイドラインがあります。
この資料は平成30年に作成が為されたあと、何度かの改定があり、現在は令和4年7月改定版がリリースされています。
副業者について企業として対応が必要な点は、競業・守秘義務を除けば、やはり労働時間管理、過重労働対策です。
結論としては、自社での残業時間と副業先での労働時間を合計して、過労死ラインの月80時間を超えないように、コントロールしていきましょう、というのが1つの基準・指針となります。
このあたりの副業者に対する考え方についてガイドラインに記載がありますので、企業のご担当者はこのガイドラインに目を通しておきましょう。
社労士目線・専門家の視点からのアドバイス
社内様式の副業許可申請書を作成して運用しましょう
では、実際に社員から副業の希望があった場合はどのような対応をすべきでしょうか?
弊社がおすすめする対応法は、就業規則で大枠のルールを決めておき、実際に個別に希望者が発生したときには、個別に許可申請をあげてもらうやり方です。
企業ごとに就業規則の内容に応じて、申請書のフォーマットを作成しておき、その申請書に基づいて副業の許可申請を行ってもらう、というやり方になります。
許可申請書については、特に法定様式のようなものはありませんので、任意で書式を作成することになりますが、以下の内容を盛り込むことをお勧めしております。
副業先の情報:副業先の会社名、所在地、業種、業務内容を正確に記載します。これにより、本業との競業避止や利益相反を防ぐことができます。
副業の契約形態:副業が雇用なのか、個人事業なのか、業務委託なのかによって、労働時間を通算するべきなのかどうかも変わってきます。ここは重要な論点となります。
勤務形態と時間:副業での雇用形態(正社員、アルバイト、契約社員など)や勤務時間、勤務日数を具体的に明示します。本業への影響を最小限に抑えるための配慮が必要です。
誓約事項:副業が本業に支障をきたさないこと、会社の機密情報を漏洩しないことなど、会社の規定に従う旨を明記します。
これらの項目を網羅した申請書を作成することで、トラブルを予防することができます。
副業に関する労働時間の通算ルールを把握・理解しておきましょう。
副業を行った場合は、複数の勤務先での労働時間は通算される、という複雑なルールがあります。具体的には以下のような制限、ルールが定められています。
- 使用者は、労働者の自己申告などで、副業・兼業先での労働時間を把握し、自社での労働時間と通算しなければいけません。
- 副業・兼業先での労働時間を自社での労働時間と合わせた結果、自社での労働時間が、1週40時間または1日8時間を超える法定外労働に当たる場合、36協定の締結、届出、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。
- さらに、自社と副業・兼業先での法定外労働の時間と休日労働の時間を合わせて、単月100時間未満、複数月平均80時間以内とする必要があります。
実はこれが、かなり大変です。
労働基準法の昔からの考えが残っており、副業が解禁された現在の働き方にそぐわなくなってきていますが、現状は上記のルールが原則となります。
労働時間の通算管理は、企業にとっても労働者にとっても重要です。企業は労働者から他の勤務先での労働時間を申告してもらい、適切に管理する責任があります。一方、労働者は自身の総労働時間を把握し、過重労働にならないよう注意する必要があります。
一方で、現行のこの労働時間通算ルールは、企業側の管理負担が大きいとの指摘があります。そのため、政府は副業・兼業を促進するために、労働時間通算の見直しを検討しています。
具体的には、労働時間の通算管理の廃止や、企業の管理責任の軽減が議論されています。これにより、副業・兼業がより行いやすくなることが期待されています。
労働時間の通算管理は、労働者の健康と安全を守るための重要な仕組みです。副業を行う際は、自身の労働時間を適切に管理し、過重労働を避けるよう心掛けましょう。
副業の際の労働時間通算の除外の動き(法改正動向)
副業・兼業の普及に伴い、労働時間通算に関する法改正の動きが現在進んでいます。(まだ決定されてはいません)
現在の労働基準法の規定、解釈では、労働者が複数の事業場で働く場合、その労働時間を通算することが求められていますが、この規定は企業にとって管理負担が大きく、副業促進の障害となっています。
2024年9月、政府は副業・兼業を促進するため、労働時間通算の管理ルールを見直す方針を示しました。
具体的には、労働時間の通算管理の廃止や、企業の管理責任の軽減が検討されています。この見直しにより、企業は副業者の労働時間を個別に管理する負担が軽減され、副業・兼業がより行いやすくなることが期待されています。
しかし、労働時間通算の除外は、労働者の健康管理や過重労働防止の観点から慎重な議論が必要という意見も根強くあります。
労働時間通算の廃止により、労働者が長時間労働に陥るリスクが高まる可能性も考えられます。そのため、法改正に際しては、労働者の健康と安全を守るための新たな仕組みやガイドラインの整備が求められます。
今後の法改正の動向を注視しつつ、企業と労働者は適切な労働時間管理を行い、副業・兼業の健全な普及を目指すことが重要です。
副業者の取扱いを相談したい方へ
いかかでしたでしょうか?
ここまで、副業と就業規則の規定や実際に副業者がでた場合の対応法などについてご説明致しました。
就業規則に新しく副業の取扱いも規定したい、今ある副業の規定を変えたい、副業の取扱いについて相談したい、という方はぜひ一度弊所にご相談下さい。
その際、自社の就業規則が既にある場合は、その資料も持参してご相談に来られるとより具体的なアドバイスが可能です。
- 就業規則に副業規定を追加したい
- 副業の社内管理書式を整備したい
- 実際に副業を許可したものの、社員のパフォーマンスが低下して問題が起こってしまった
- 副業、ダブルワークの制度を整備したい
- 社員から副業の希望が出ているが、どのように進めればいいかわからない
このような副業に関する悩みがある企業様、副業の取扱いについて就業規則専門の社会保険労務士へ相談し、改めて検討してみませんか?
当法人へのご相談の流れ
お問合せからご相談、契約までの流れをご説明します。
お問合せ

まずは電話または問合せフォームにてお問合せください。
初回面談

相談を希望される方はオンラインまたは当法人へお越し頂きお話を伺います。
ご契約

ご依頼内容に応じて見積を提示致しますので、内容をご確認下さい。ご確認後、契約書を作成致します。
お問合せはこちら
東京都千代田区のコントリビュート社会保険労務士法人のホームページにお越し頂き、ありがとうございます。当法人は就業規則の作成・改定を専門とする社会保険労務士法人です。
お電話でのお問合せはこちら
03-6264-8320
千代田区・中央区・港区をはじめとした人事担当者、経営者の方のご相談をお待ちしております。
■東京都千代田区神田錦町3-6-602
■受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)